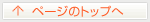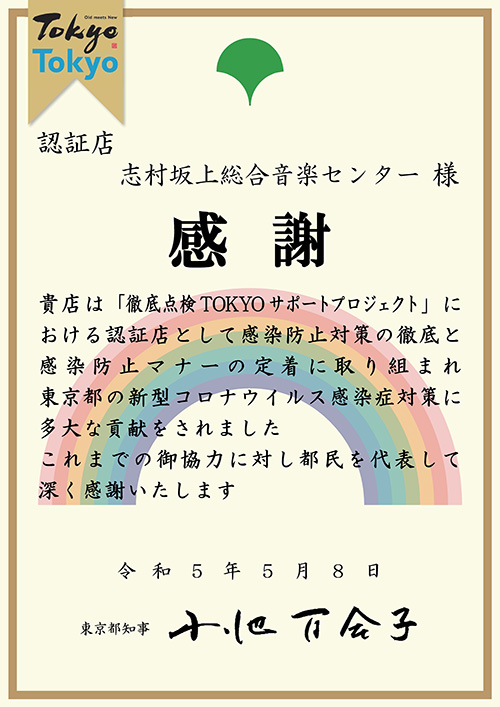皆さんはどんな曲が好きで、普段どんな音楽を聴いていますか?クラシック音楽も時代により様々です。勿論クラシックだけではなく、 色々なジャンルの曲を沢山沢山聴いて、音楽をより楽しんで下さい。
バロックLet's Listen!
短調・長調のしくみが確立され多声音楽が作られ和声音楽も起こりました。オペラ・オラトリオなどの劇音楽も生まれ器楽も発達しフーガや組曲が作られました。この頃、ピアノが始めて製造されます。(音域は4オクターブ位)










古典派Let's Listen!
和声音楽が主流となります。交響曲、ソナタ、室内楽、協奏曲など、ソナタ形式をもとにした楽曲が多く作られました。








ロマン・国民楽派Let's Listen!
自由な感情の表現を重んじる傾向が強まり、また、民族色の強い音楽が作られました。即興曲、無言歌、ラプソディなどの器楽の小曲や、交響詩などの表題音楽、あるいは芸術歌曲やオペラが盛んに作られました。和音の扱いや管弦楽の音色が多彩になりました。



























近代・現代Let's Listen!
近代・現代
 クロード・アシル・ドビュッシー・(1862-1918)・フランス・代々農業や手工業に従事してきた庶民の家系で、陶器店を営む両親の長子として生まれました。9才の時叔母のきもいりでチェルッティ Jean Ceruttiにピアノの手ほどきを受けました。彼は古いピアノの前で夢想にふける様になりました。そんな彼に興味を持ってレッスンをつけ、両親を説いて彼に音楽の道を歩ませる様に力を尽くしたのは、詩人ヴェルレーヌの義母でショパンの弟子、 モーテ・ド・フルールヴィル夫人Maute-de-Fleurville でありました。彼女のおかげで1872年10月パリ音学院に入学、84年6月までの10年余りをそこの学生として送りました。ヴァイオリンソナタ「Minstrels」前奏曲集第1巻より第12曲
クロード・アシル・ドビュッシー・(1862-1918)・フランス・代々農業や手工業に従事してきた庶民の家系で、陶器店を営む両親の長子として生まれました。9才の時叔母のきもいりでチェルッティ Jean Ceruttiにピアノの手ほどきを受けました。彼は古いピアノの前で夢想にふける様になりました。そんな彼に興味を持ってレッスンをつけ、両親を説いて彼に音楽の道を歩ませる様に力を尽くしたのは、詩人ヴェルレーヌの義母でショパンの弟子、 モーテ・ド・フルールヴィル夫人Maute-de-Fleurville でありました。彼女のおかげで1872年10月パリ音学院に入学、84年6月までの10年余りをそこの学生として送りました。ヴァイオリンソナタ「Minstrels」前奏曲集第1巻より第12曲
 ジャン・シベリウス・(1865-1957)・フィンランド・父は軍医であったクリスティアン・グスタフ Christian-Gustaf (1821-1868)母はマリア・シャルロッタ Maria Charlotta (1821-1897)。シベリウスには姉と弟がいました。 彼がわずか2歳8ケ月にしかならない時に、父はみごもった母を残して、チフスにかかって急死しました。
それ以来、一家はハメーンリンナに住む母方の祖母である牧師の未亡人のもとに身を寄せて生活しております。この家に未婚の娘ユリアJuliaがいましたが、ピアノがうまく、シペリウスが5才になった時に、その手ほどきを受けるようになりました。シペリウスは練習曲を好まず、自由な即興を楽しんでいました。フィンランディア
終結部
ジャン・シベリウス・(1865-1957)・フィンランド・父は軍医であったクリスティアン・グスタフ Christian-Gustaf (1821-1868)母はマリア・シャルロッタ Maria Charlotta (1821-1897)。シベリウスには姉と弟がいました。 彼がわずか2歳8ケ月にしかならない時に、父はみごもった母を残して、チフスにかかって急死しました。
それ以来、一家はハメーンリンナに住む母方の祖母である牧師の未亡人のもとに身を寄せて生活しております。この家に未婚の娘ユリアJuliaがいましたが、ピアノがうまく、シペリウスが5才になった時に、その手ほどきを受けるようになりました。シペリウスは練習曲を好まず、自由な即興を楽しんでいました。フィンランディア
終結部
 ジョゼフ・モーリス・ラベル・(1875-1937)・フランス・スイス国籍を持つ鉄道技師の父ピエール・ジョゼフと、バスク地方の出の母マリー・ドルアールの長男としてスペイン国境に近いシブールに生まれました。生後三か月目に一家はパリに移住しております。好楽家であった父の理解のもとに7才からピアノの学習を始めましたが、最初は他の子供達の多くと同様、 父のほうびに励まされての事でありました。1887年ルネ Charles Rene より和声法の勉強を始め、やがて作曲も始めました。その様な幼少時の試作にあっても、すでに後年のラヴェルの特質である首尾の完全な一貫性と、旋律の独創性を持っていたと、ルネは後に語っています。ボレロ(最終部分)
ジョゼフ・モーリス・ラベル・(1875-1937)・フランス・スイス国籍を持つ鉄道技師の父ピエール・ジョゼフと、バスク地方の出の母マリー・ドルアールの長男としてスペイン国境に近いシブールに生まれました。生後三か月目に一家はパリに移住しております。好楽家であった父の理解のもとに7才からピアノの学習を始めましたが、最初は他の子供達の多くと同様、 父のほうびに励まされての事でありました。1887年ルネ Charles Rene より和声法の勉強を始め、やがて作曲も始めました。その様な幼少時の試作にあっても、すでに後年のラヴェルの特質である首尾の完全な一貫性と、旋律の独創性を持っていたと、ルネは後に語っています。ボレロ(最終部分)
 滝廉太郎・(1879-1903)・日本・
作曲家・ピアノ奏者。1894年(明治27年)高等師範付属音楽学校(のちの東京音楽学校)に入学。幸田延、ケーベルに師事。98年専修科から研究家に進みユンケルに師事。同年の東音秋季音楽会でバッハのイタリア協奏曲を独奏してピアノ奏者としての頭角を表す。また彼は洋楽揺繁期における最初の本格的作曲家であり、洋楽スタイルによる最初の芸術作品である組歌「四季」は近代音楽史上極めて重要な作品。ヨーロッパ古典派または初期ロマン派的なスタイルであるが、日本風な表現を意図してヨナ抜き短音階による「荒城の月」も注目される。荒城の月
滝廉太郎・(1879-1903)・日本・
作曲家・ピアノ奏者。1894年(明治27年)高等師範付属音楽学校(のちの東京音楽学校)に入学。幸田延、ケーベルに師事。98年専修科から研究家に進みユンケルに師事。同年の東音秋季音楽会でバッハのイタリア協奏曲を独奏してピアノ奏者としての頭角を表す。また彼は洋楽揺繁期における最初の本格的作曲家であり、洋楽スタイルによる最初の芸術作品である組歌「四季」は近代音楽史上極めて重要な作品。ヨーロッパ古典派または初期ロマン派的なスタイルであるが、日本風な表現を意図してヨナ抜き短音階による「荒城の月」も注目される。荒城の月
 バルトーク・ベーラ・ヴィクトル・ヤーノシュ・(1881-1945)・ハンガリー・作曲家・民族音楽学者・ピアノ奏者。20世紀前半における最も優れた音楽家の一人であると同時に、コダーイと共にハンガリー民族音楽の収集と研究に卓越した業績を残しています。農業学校の校長を務める父ベーラと母ヴォイト・パウラの長男に生まれました。父はピアノとチェロを奏し、小曲を作曲し、母親はピアノを弾きました。父の死後、母親からピアノを学び、
9才のころより作曲を始めております。管弦楽の為の協奏曲第5楽章
バルトーク・ベーラ・ヴィクトル・ヤーノシュ・(1881-1945)・ハンガリー・作曲家・民族音楽学者・ピアノ奏者。20世紀前半における最も優れた音楽家の一人であると同時に、コダーイと共にハンガリー民族音楽の収集と研究に卓越した業績を残しています。農業学校の校長を務める父ベーラと母ヴォイト・パウラの長男に生まれました。父はピアノとチェロを奏し、小曲を作曲し、母親はピアノを弾きました。父の死後、母親からピアノを学び、
9才のころより作曲を始めております。管弦楽の為の協奏曲第5楽章
 イーゴリ・フョードロヴィチ・ストラヴィンスキー・(1882-1971)・ロシア→アメリカ・彼の父フョードル Fyodor-Ignat'evich(1843-1902)は、ペテルブルグのマリインスキー劇場に26年も務めた 有名な主役バス歌手。愛書家で絵画の造詣も深かった彼は、衣装や扮装にかけても 当時の第一人者でありました。若いイーゴリはこの様な家庭に育ち、ピアノを学び作曲を試み、またグリンカ,チャイコフスキー,ダルゴムイシスキー,ムソルクスキーらの作品に接することができました。しかし、両親は彼を音楽家にする意思は無くペテルブルク大学に入れて法律を学ばせました。ここで、リムスキー・コルサコフの末息子と知り合い、彼は音楽の道に進む事となります。「春の祭典」より春の兆しと若い娘の踊り
イーゴリ・フョードロヴィチ・ストラヴィンスキー・(1882-1971)・ロシア→アメリカ・彼の父フョードル Fyodor-Ignat'evich(1843-1902)は、ペテルブルグのマリインスキー劇場に26年も務めた 有名な主役バス歌手。愛書家で絵画の造詣も深かった彼は、衣装や扮装にかけても 当時の第一人者でありました。若いイーゴリはこの様な家庭に育ち、ピアノを学び作曲を試み、またグリンカ,チャイコフスキー,ダルゴムイシスキー,ムソルクスキーらの作品に接することができました。しかし、両親は彼を音楽家にする意思は無くペテルブルク大学に入れて法律を学ばせました。ここで、リムスキー・コルサコフの末息子と知り合い、彼は音楽の道に進む事となります。「春の祭典」より春の兆しと若い娘の踊り
 アルフレード・カゼッラ・(1883-1947)・イタリア・幼少から母の手ほどきでピアノを始める。1896年パリ音楽院に入学し、1900年からはフォーレに師事。1908年には作曲家、指揮者として自作の第一交響曲ロ短調をもってデビュー。第2作曲期にはストラビンスキー、第3作曲期にはR.シュトラウスやマーラーの影響を受ける。彼は現代イタリアのすぐれた作曲家であったばかりでなく、評論や著書を通じてまた指揮者、ピアノ奏者として、あるいは3重楽団「Trio Italiano」における演奏活動など多方面にわたる偉大な指導者であった。6つの練習曲 OP.70より「no.1, Sulle Terze Maggiori」
アルフレード・カゼッラ・(1883-1947)・イタリア・幼少から母の手ほどきでピアノを始める。1896年パリ音楽院に入学し、1900年からはフォーレに師事。1908年には作曲家、指揮者として自作の第一交響曲ロ短調をもってデビュー。第2作曲期にはストラビンスキー、第3作曲期にはR.シュトラウスやマーラーの影響を受ける。彼は現代イタリアのすぐれた作曲家であったばかりでなく、評論や著書を通じてまた指揮者、ピアノ奏者として、あるいは3重楽団「Trio Italiano」における演奏活動など多方面にわたる偉大な指導者であった。6つの練習曲 OP.70より「no.1, Sulle Terze Maggiori」
 山田耕作・(1886-1965)・日本・作曲家・指揮者。
1904年(明治37年)東京音楽学校に入学、予科から本科声楽科に進み1908年に卒業、研究科に進学。彼の創作活動はヴァーグナーやR.シュトラウスの影響の濃いベルリン時代(1910-1913)の楽劇や交響詩から、1910年代後半の舞踏詩へと進展。1920年代の山田は北原白秋と交わって詩と音楽の理念的融合をはかり、
日本語のアクセントと語感を尊重する芸術的歌曲を創造するが、やがてわらべうたの音階を利用した童謡を繰り返し作曲するようになる。
その後1920年代末から1930年代にかけて「序景」「あやめ」を過渡的作品とした舞踏詩と歌曲からオペラへと進む。また、滝廉太郎の「荒城の月」
を彼の没後の1917年にオリジナルのロ短調から短3度上のニ短調に移調し、旋律にある臨時記号を外した。ジプシー音階の特徴を無くし、より日本的な旋律にするためだった。
この道
山田耕作・(1886-1965)・日本・作曲家・指揮者。
1904年(明治37年)東京音楽学校に入学、予科から本科声楽科に進み1908年に卒業、研究科に進学。彼の創作活動はヴァーグナーやR.シュトラウスの影響の濃いベルリン時代(1910-1913)の楽劇や交響詩から、1910年代後半の舞踏詩へと進展。1920年代の山田は北原白秋と交わって詩と音楽の理念的融合をはかり、
日本語のアクセントと語感を尊重する芸術的歌曲を創造するが、やがてわらべうたの音階を利用した童謡を繰り返し作曲するようになる。
その後1920年代末から1930年代にかけて「序景」「あやめ」を過渡的作品とした舞踏詩と歌曲からオペラへと進む。また、滝廉太郎の「荒城の月」
を彼の没後の1917年にオリジナルのロ短調から短3度上のニ短調に移調し、旋律にある臨時記号を外した。ジプシー音階の特徴を無くし、より日本的な旋律にするためだった。
この道
 セルゲイ・セルゲーエヴィチ・プロコフィエフ・(1891-1953)・ソ連・ピアノ奏者・指揮者。農学者の家に生まれ、ピアノ奏者・教育者の母により幼時から音楽及び仕事に対する組織性と責任感を厳しく教えられました。5歳半でピアノ曲<インドのギャロップ>を、9歳でオペラ<巨人>を作曲しております。1902年モスクワでS.タネーエフに才能を認められ、その勧めでグリエールらに指導を受け、翌年にかけて第1交響曲、オペラ <ペスト流行期の酒宴>、他にピアノ小曲多数を作曲して並みはずれた成熟を示しております。ピーターと狼
セルゲイ・セルゲーエヴィチ・プロコフィエフ・(1891-1953)・ソ連・ピアノ奏者・指揮者。農学者の家に生まれ、ピアノ奏者・教育者の母により幼時から音楽及び仕事に対する組織性と責任感を厳しく教えられました。5歳半でピアノ曲<インドのギャロップ>を、9歳でオペラ<巨人>を作曲しております。1902年モスクワでS.タネーエフに才能を認められ、その勧めでグリエールらに指導を受け、翌年にかけて第1交響曲、オペラ <ペスト流行期の酒宴>、他にピアノ小曲多数を作曲して並みはずれた成熟を示しております。ピーターと狼
 ファーディ・グローフェ・(1892-1972)・アメリカ・ピアノとヴァイオリンを母に、ヴィオラを祖父に学ぶ。20才でロスアンジェルス交響楽団のヴィオラ奏者になりますが、1919年ホワイトマンに会い、その楽団で13年間編曲者、ピアノ奏者を務めます。24年ガーシュインの <ラプソディー・イン・ブルー>のオーケストレーションを受け持ちました。彼の編曲法の特徴は、サクソフォーン群や細分された弦楽器群で奏される減7や減9の和音の跳躍の少ない連続が作り出す甘い感性にあり、当時「シンフォニック・ジャズ」としてもてはやされました。31年の <グランド・キャニオン組曲 Grand CanyonSuite>で作曲家として成功。その作風はきわめて描写的。ミシシッピ組曲からハックルベリー・フィン
ファーディ・グローフェ・(1892-1972)・アメリカ・ピアノとヴァイオリンを母に、ヴィオラを祖父に学ぶ。20才でロスアンジェルス交響楽団のヴィオラ奏者になりますが、1919年ホワイトマンに会い、その楽団で13年間編曲者、ピアノ奏者を務めます。24年ガーシュインの <ラプソディー・イン・ブルー>のオーケストレーションを受け持ちました。彼の編曲法の特徴は、サクソフォーン群や細分された弦楽器群で奏される減7や減9の和音の跳躍の少ない連続が作り出す甘い感性にあり、当時「シンフォニック・ジャズ」としてもてはやされました。31年の <グランド・キャニオン組曲 Grand CanyonSuite>で作曲家として成功。その作風はきわめて描写的。ミシシッピ組曲からハックルベリー・フィン
 ジョージ・ガーシュウィン・(1898-1937)・アメリカ・ブルックリンの移民地区にロシア系ユダヤ人の息子として生まれました。10才の時、級友の弾くドヴォルジャークの ヴァイオリン曲<ユモレスク>に感動したのを契機として、音楽が彼の全生活を占めるようになり、ピアノと和声法を学びました。R.ゴールドマン,カウエル,シリンガーらに教えを受けております。ラプソディ・イン・ブルー
ジョージ・ガーシュウィン・(1898-1937)・アメリカ・ブルックリンの移民地区にロシア系ユダヤ人の息子として生まれました。10才の時、級友の弾くドヴォルジャークの ヴァイオリン曲<ユモレスク>に感動したのを契機として、音楽が彼の全生活を占めるようになり、ピアノと和声法を学びました。R.ゴールドマン,カウエル,シリンガーらに教えを受けております。ラプソディ・イン・ブルー
 アラム・イリイチ・ハチャトゥリアン・(1903-1978)・ソ連・彼は製本工の子として生まれました。商業学校在学中、南カフカスの民族音楽に親しみました。1921年モスクワに行き、モスクワ大学理工学部に在学ののち音楽的才能が認められ、グネーシン音楽学校に入学。チェロを学び、次いでゲネーシンの作曲クラスに入りました。組曲「スパルタクス」より第3番/第3曲「エジプトの乙女の踊り」
アラム・イリイチ・ハチャトゥリアン・(1903-1978)・ソ連・彼は製本工の子として生まれました。商業学校在学中、南カフカスの民族音楽に親しみました。1921年モスクワに行き、モスクワ大学理工学部に在学ののち音楽的才能が認められ、グネーシン音楽学校に入学。チェロを学び、次いでゲネーシンの作曲クラスに入りました。組曲「スパルタクス」より第3番/第3曲「エジプトの乙女の踊り」
 ドミートリイ・ドミートリエヴィチ・ショスタコーヴィチ・(1906-1975)・ソ連・ポーランドの独立運動(1831年)に参加してウラルに流刑にされたポーランド人の血を引く父と、シベリア金山の監督官の娘である母との間に生まれた一人息子で、姉マリヤ(ピアノ奏者)と妹ゾーヤ(科学者)がいました。父ドミトリー・ボレスラヴォヴィチはペテルブルグ大学理学部卒、メンデレーエフの度量衡管理局の上級検査官であったが、美声の持主で自分でもよく歌う音楽愛好家であった。母ソフィアはペテルブルグ音楽院卒の本格的なピアノ奏者で、彼に音楽の手ほどきをした。ショスタコヴィチは、ビューローに学んだこともあるというポーランド人グリャッセル I.A.Gliasserの音楽教室で学んだ後、グラズノフの個人的な勧めもあって、1919年ペトログラード音楽院に入学、ピアノを母の師でもあるロザノヴァ A.A.Rozanovaとニコラエフに、作曲をシテインベルクに師事した。「革命」交響曲・第5番第4楽章/冒頭部
ドミートリイ・ドミートリエヴィチ・ショスタコーヴィチ・(1906-1975)・ソ連・ポーランドの独立運動(1831年)に参加してウラルに流刑にされたポーランド人の血を引く父と、シベリア金山の監督官の娘である母との間に生まれた一人息子で、姉マリヤ(ピアノ奏者)と妹ゾーヤ(科学者)がいました。父ドミトリー・ボレスラヴォヴィチはペテルブルグ大学理学部卒、メンデレーエフの度量衡管理局の上級検査官であったが、美声の持主で自分でもよく歌う音楽愛好家であった。母ソフィアはペテルブルグ音楽院卒の本格的なピアノ奏者で、彼に音楽の手ほどきをした。ショスタコヴィチは、ビューローに学んだこともあるというポーランド人グリャッセル I.A.Gliasserの音楽教室で学んだ後、グラズノフの個人的な勧めもあって、1919年ペトログラード音楽院に入学、ピアノを母の師でもあるロザノヴァ A.A.Rozanovaとニコラエフに、作曲をシテインベルクに師事した。「革命」交響曲・第5番第4楽章/冒頭部
 サミュエル・バーバー・(1910-1981)・アメリカ・彼の作風は古典的な形式や書法を用い、甘美なメロディと彼自身の生命力に満ちた表現を用いる。1936年ローマ在学中に書いた<一楽章の交響曲>はしばしば演奏される。1937年の<弦楽のためのアダージオ><管弦楽のための第1エッセー>は1938年トスカニーニによって初演された彼の初期の代表作。1942年にヴァイオリン協奏曲、1944年には空軍に委嘱されて交響曲第2番を書いた。この曲では無線誘導ビームの音をオスティナートで扱ったり飛行機の爆音の擬音効果を入れたりしている。弦楽のためのアダージョ
サミュエル・バーバー・(1910-1981)・アメリカ・彼の作風は古典的な形式や書法を用い、甘美なメロディと彼自身の生命力に満ちた表現を用いる。1936年ローマ在学中に書いた<一楽章の交響曲>はしばしば演奏される。1937年の<弦楽のためのアダージオ><管弦楽のための第1エッセー>は1938年トスカニーニによって初演された彼の初期の代表作。1942年にヴァイオリン協奏曲、1944年には空軍に委嘱されて交響曲第2番を書いた。この曲では無線誘導ビームの音をオスティナートで扱ったり飛行機の爆音の擬音効果を入れたりしている。弦楽のためのアダージョ
印象派の音楽や12音音楽などの新しい音楽が生まれました。電子音や生活の中の噪音を用いた音楽なども生まれました。交通や録音技術などの発達により、世界中の音楽が居ながらにして楽しめるようになりました。(参考文献 平凡社 音楽大辞典)